乾電池だと電池切れになってしまって交換が発生するので消費電力が大きな機器にはできるだけ乾電池を避けたいものです。
ただどうしても電池を入れるような構造になってしまっているものは、ACアダプタをつけようと思っても電極にはんだ付けしたりと機器側を改造しないといけません。
できれば改造せずにACアダプタで電源を供給したいので、ダミー電池というものを利用しようと考えました。
電池からACアダプタへ置き換えるためのダミー電池


乾電池だと電池切れになってしまって交換が発生するので消費電力が大きな機器にはできるだけ乾電池を避けたいものです。
ただどうしても電池を入れるような構造になってしまっているものは、ACアダプタをつけようと思っても電極にはんだ付けしたりと機器側を改造しないといけません。
できれば改造せずにACアダプタで電源を供給したいので、ダミー電池というものを利用しようと考えました。

プリント基板の業者ではよくElecrowを使っています。
個人的に早くて安い印象がありますが、品質が悪くなってきてると感じたので違う業者を探し中です。

ニキシー管時計に不可欠なニキシー管は、非常に古いデバイスですので新品であっても壊れていることがあります。
長期保存していますのでどうしても避けられないですが、思っているより不良率が高いという。

相変わらず3Dプリンタは ダヴィンチ Jr. 1.0w を使っていますが、
PLAの強度に不満はありつつなんだかんだ文句はほとんどなく使えています。
それでもABSとかもうちょっと強度のある材料が使えたらいいなとは思っていました。
そう思っていたとき、最近XYZwareをアップデートしてみると、「Tough PLA」という項目があったのでそれを試してみることにしました。

ニキシー管時計を生産して基板がはけてきました。
今のバージョンの基板が少なくなってきました。
そして懲りずに現在も設計を続けています。

本年も「なんでも独り言」をよろしくお願いします。
昨年は大変でしたが目標通り変化がちゃんとあった年になりました。

「鍵閉めるのが面倒、ホテルみたいにオートロックだったらいいのに」とふと思ったので自宅ドアのスマートロックシステムを速攻で作ってしまいました。
鍵の開け閉めにはRFIDカードと内側からのボタン操作に対応しています。
セキュリティ的な配慮として、登録しているカードのみで開けることができるようにしています。

連載が終わってから早いですが、再びお声をかけてくださり記事を書かせていただきました。
今回はTwitterで思ったより評判だったあの記事です。

私はHAKKOのFX-888Dというはんだごてを使っています。
ステーション型のそこそこのお値段のするはんだごてなので、はんだ付け後に汚れていると気になってしまいついつこて先を磨いています。
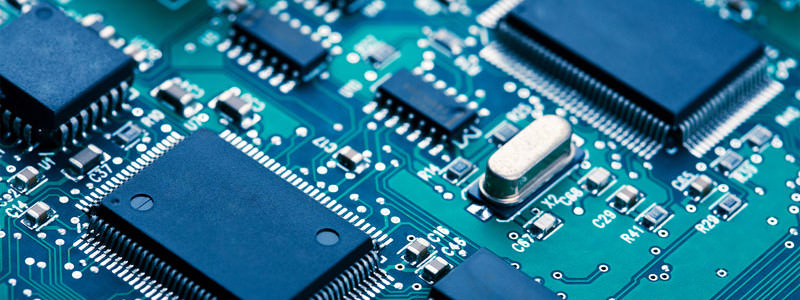
安価な「USB-シリアル変換器」としてCP2102のモジュールをよく使っているのですが、偽物(不良品)が多い事を知りました。
CP2102自体はAliexpressで安価に売っていて5Vトレラントなのがいいんですよね。
偽物は3.3Vなのに4.3Vほど出てしまう仕様になっているようです。