連載なので当たり前ですが。
以前、編集さんに提出していたもので、気付いたら載っていました。


今安定化電源が自作品を含めると6台あります。
どう考えても持ちすぎです。
安物買いの銭失いという感じなのですが。

「冷やし中華はじめました」的なノリです。
と言っても求人を探し始めてから1ヶ月くらい経ってますけどね。
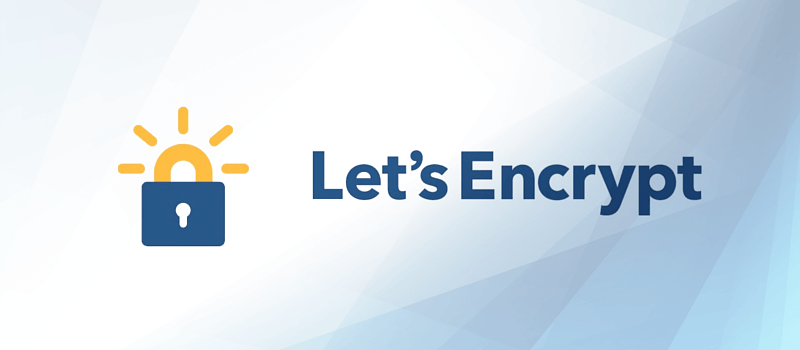
Googleさんから「HTTPS化しろ」とおどされたので、仕方なくHTTPS化してみました。
SSLサーバ証明書は Let's Encrypt で発行していますので無料です。
さくらのレンタルサーバを利用しているのでちょっと面倒だったんですけどね・・・
更新したてで表示がおかしくなる場合がありますので、キャッシュを削除していただけると幸いです。

ただのブロガーの私が、工学社さんの老舗雑誌「月刊I/O」で記事を書かせていただきました。
ちょっとじゃないです、がっつり3ページ分です。
さらに連載ですので9月号だけではなく、それ以降も寄稿予定です。

土日を使って1泊2日の東京旅行に行ってきました。
といっても目的はやっぱりMFTなんですけどね。
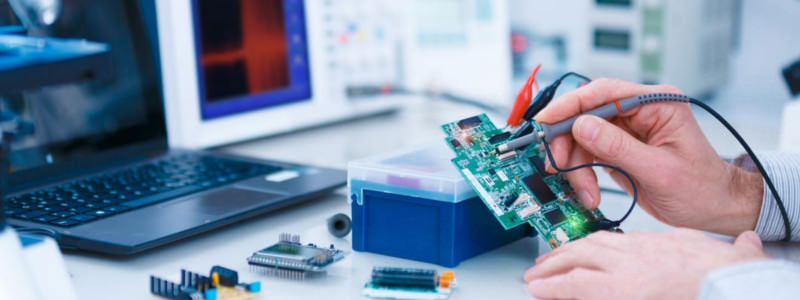
ESP8266(ESP-WROOM-02)やESP32(ESP-WROOM-32)は小型でWi-Fi接続ができて非常に便利なのですが、電源周りをしっかりとする必要のあるデバイスです。
電源がひ弱だとWi-Fi接続できなかったり、リセットを繰り返したり不安定になってしまうのでしっかりと対策しなければなりません。

しばらく使わずにいた、3Dプリンタ(ダヴィンチ Jr. 1.0w)を久しぶりに起動しました。
ソフトウェアとドライバをアップデートして、「さあ印刷!」というところで、なぜかWi-Fi接続できなくなっていました。
その時は渋々USB接続に切り替えて印刷したのですが、なぜWi-Fi接続できなくなったのかわからなかったので原因を突き詰めることにしました。

マイコンやArduinoのシリアル通信を受信したり、送信したりするためのシリアルモニタはPCであればTeraTermやArduino IDE に付属しているシリアルモニタを使っています。
ですが、PCから機器にケーブルが届かなかったり、外だったりするとデスクトップPCは使えないですからノートPCを使うことになりますが、それはそれで大型で不便です。
Androidアプリであれば携帯できて非常に便利ですので、私が独断で使いやすいと思ったシリアルモニタのアプリを紹介します。

タイトルで既にオチてますが。
少し前に記事でプリント基板を発注したとお伝えしました。
速攻で届いたので、すごく嬉しかったのですが開けてみると全部不良品でしたorz
シルクが全部かすれているという不良でした。
その他は問題ないのですが。