「電子工作」が趣味ならば、趣味用名刺もそれをコンセプトに作れば面白いと感じたので、「だったらプリント基板でつくろう」という考えに至りました。
そこそこ単価は高いのですが...
何回も変更を重ねているのですが、ようやく及第点かなというところまで来ましたので作品として紹介しようかと思います。

「電子工作」が趣味ならば、趣味用名刺もそれをコンセプトに作れば面白いと感じたので、「だったらプリント基板でつくろう」という考えに至りました。
そこそこ単価は高いのですが...
何回も変更を重ねているのですが、ようやく及第点かなというところまで来ましたので作品として紹介しようかと思います。

ESP8266はプログラムの無線書き込みができる機能(OTA:On The Air)があるらしいというのを最近知ったので実際にやってみました。
一度書き込み用のプログラムを入れると次からは端子の接続不要で書き込めるのが魅力的です。
「ArduinoOTA」は標準で入っているライブラリで、サンプルプログラムを真似すれば簡単に導入できます。

時計ばかり作っている気がしますが、新しく作っては古いのを分解しているので数はあまり増えてはいません。
置き時計に関しては自分にあったものが売ってないので、ただ気に入らないだけですが、理想を形にするため追求している感じです。

基板をはんだ付けするために固定するためのツールを色々試しているのですが、未だに「これ!」というものに巡り合っていません。
つかみ代が大きかったり、高さが微妙だったり・・・
なにかと要望が多くて使い分けができていないだけかもしれませんが。


Elecrowが安かろう悪かろうなイメージが付いてしまったので、他社も検討しようということで昔からあるSeeed Studioのプリント基板サービスである「Fusion PCB」を試してみました。

Visual Studio や VSCodeはIntellisenseが使えて開発効率が上がるので重宝しています。
一方、Arduino IDE はシンプルなのはいいのですが、ようやくベータ版で補完機能が使えるようになる感じで機能としてはいまいちというイメージがまだ拭えません。
そこで「Arduino for Visual Studio」というプラグイン(?)を使って Visual StudioでのArduino開発を試してみました。
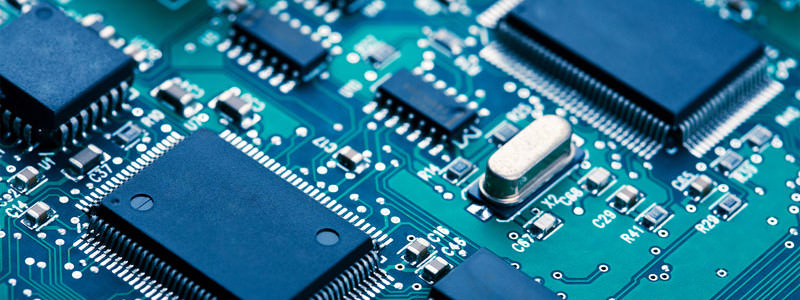
だいぶ遅れていますが、FPGArduinoという存在を最近知りました。
FPGAにArduinoコアを実装しているものです。
もちろんArduino IDEでプログラミングができます。
対応しているボードも多く、アーキテクチャはMIPSとRISC-Vの2つがあるという充実ぶりです。

乾電池だと電池切れになってしまって交換が発生するので消費電力が大きな機器にはできるだけ乾電池を避けたいものです。
ただどうしても電池を入れるような構造になってしまっているものは、ACアダプタをつけようと思っても電極にはんだ付けしたりと機器側を改造しないといけません。
できれば改造せずにACアダプタで電源を供給したいので、ダミー電池というものを利用しようと考えました。

相変わらず3Dプリンタは ダヴィンチ Jr. 1.0w を使っていますが、
PLAの強度に不満はありつつなんだかんだ文句はほとんどなく使えています。
それでもABSとかもうちょっと強度のある材料が使えたらいいなとは思っていました。
そう思っていたとき、最近XYZwareをアップデートしてみると、「Tough PLA」という項目があったのでそれを試してみることにしました。