RS-485は送信距離も多いですし2本の電線があればノイズに強い通信できるので今でもよく使われています。
特にFA関係ではまだまだ現役の通信方式です。
私もモジュールを作るときにマイコンで外と通信するときはよく採用していますが、最近作ったモジュールでうまく動かないことがありましたので、備忘録として残しておこうと思います。
RS485の方向制御に苦戦
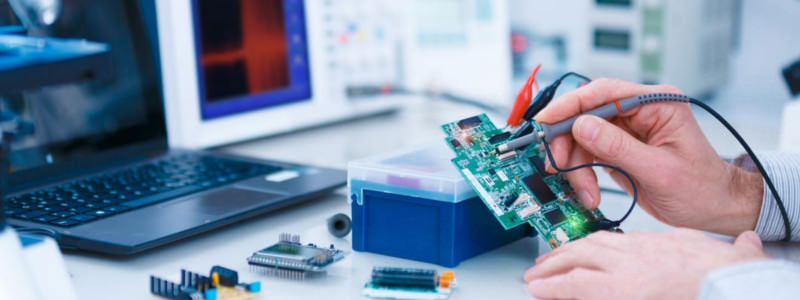
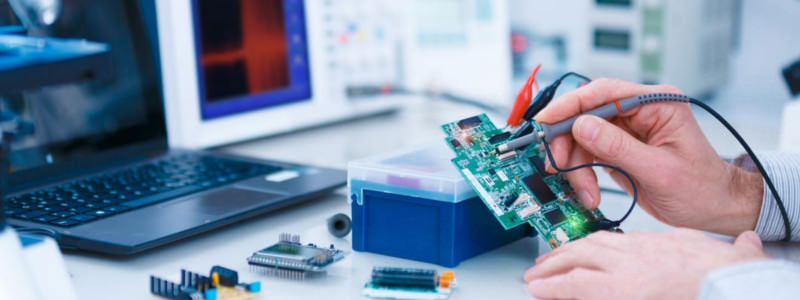
RS-485は送信距離も多いですし2本の電線があればノイズに強い通信できるので今でもよく使われています。
特にFA関係ではまだまだ現役の通信方式です。
私もモジュールを作るときにマイコンで外と通信するときはよく採用していますが、最近作ったモジュールでうまく動かないことがありましたので、備忘録として残しておこうと思います。

Twitterのタイムラインで Arduino UNO Mini Limited Edition というなんとも高級そうなArduinoを見かけました。Arduino UNO の1000万個達成記念みたいです。
The Arduino UNO is back! 😮 Introducing the UNO Mini Limited Edition... https://t.co/trLNYPOcV4 pic.twitter.com/Y6uW8wQNkf
— Arduino (@arduino) November 24, 2021

ESP32を搭載したモジュールはいくらでも見かけますが、基本的には単にI/Oを引き出したものが多いです。
通信もUARTが直接出ているくらいです。
個人的には通信インターフェースを色々と使いたいのですが、見つかりませんでしたので自作してみました。
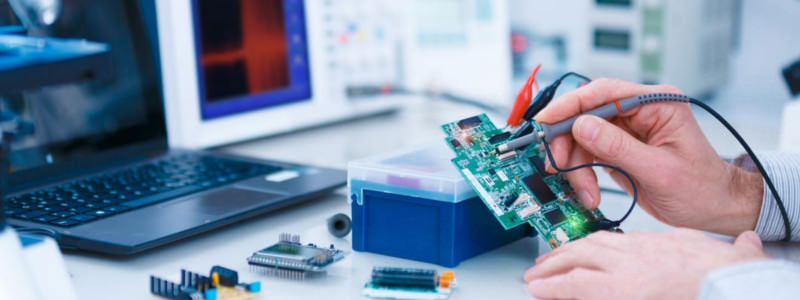
ESP8266などを使ってWi-Fiで接続できる学習リモコンを作りたいと思うことがありました。
基板を起こそうかとも考えていましたが、その時「既製品がありそう」と私の脳内センサがはたらきました。
一応検索してみたのですが、残念ながらドンピシャのものは見当たりませんでした。
しかし結構流用できそうなものが見つかったので、試しに1個買ってみて分解してみました。

以前作った水位コントローラは我ながら便利で今現在も、ちゃんと動いています。
水耕栽培の水槽の水位管理に使っています。
ただ、環境によっては電蝕が激しく、すぐに使い物にならなくなる場合もありました。
電極にもよるのですが、今のうちに電蝕対策をしておくことにしました。

以前、昔作ったユニバーサル基板製の作品をプリント基板で作り直す活動をしていたのですが、もう稼働中の作品の作り直しは終わりを迎えたと思っていました。
ただ1つ、オーディオスペアナを残して...
最近になってようやく気づいたのか重い腰を上げたのかは置いておいて、作り直しマイブームが起きた1,2年前より少しは技術力は上がったであろう現在ではどんな仕上がりになるのかが気になり、奮起して作り直してみることにしました。
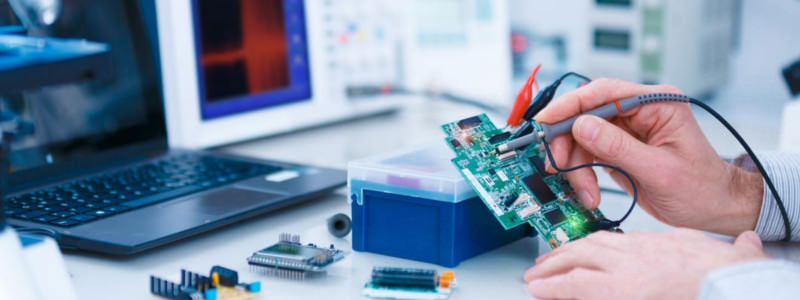
FA関係の仕事をしておりますので、よく三菱製のPLC、いわゆるシーケンサを使っています。
こういう産業機器は工場という劣悪な環境に置かれるため、非常にしっかりしています。
そのおかげもあって(?)消費者が簡単に手を出せないくらい価格が非常に高いです。
いや、普通の人はそんなものを求めないですけどね?
高い信頼性はあまり求めないから互換機はないかなと、探していると...なんと売っているという。
そんなシーケンサの怪しい互換機を試しに使ってみました。

ESP32で有線LANが使えるらしいということで以前から気になってはいました。
ただ、外付けの PHY IC のモジュールばかりが目立っていて、それらが組み込まれたモジュールがないかなとも思っていました。
他にもないのかと色々調べてみると、いいものがあったのでそれを使って自己満拡張モジュールを作ってみました。

大型の縦型水耕栽培装置を2台作りましたが、その大きさゆえにと立地的に背丈の低い葉物野菜専用になっています。
トマトみたいな果菜類も育てたいと思っていたので、余っていた部品を寄せ集めてもう1台作ってみました。

以前、空圧式のディスペンサを作ったことがあります。
アナログ操作のタイプでボリュームを回して吐出時間を調節する仕様です。
もう数年は使っていますので慣れてきましたが、どうしても正確性に欠けます。
また、制御基板がユニバーサル基板で気になっているところでしたので思い切って作り直してみました。